コラム
【2025年版】大規模修繕工事の正しい進め方とは?スケジュール・注意点・国交省ガイドラインをプロが解説
大規模修繕工事とは?
大規模修繕工事は、アパート・マンションなどの集合住宅において、建物の劣化や機能低下を防いで、長期的な資産価値を保つために行う「建物全体の改修工事」です。
日本のアパート・マンションは、築10年・20年・30年と経年劣化が進むにつれて、屋上防水・外壁・給排水管・鉄部塗装など、目に見えない部分の傷みが深刻になります。これらの劣化や損傷を放置すると、資産価値の低下や居住環境の悪化を招くため、計画的な修繕が欠かせません。
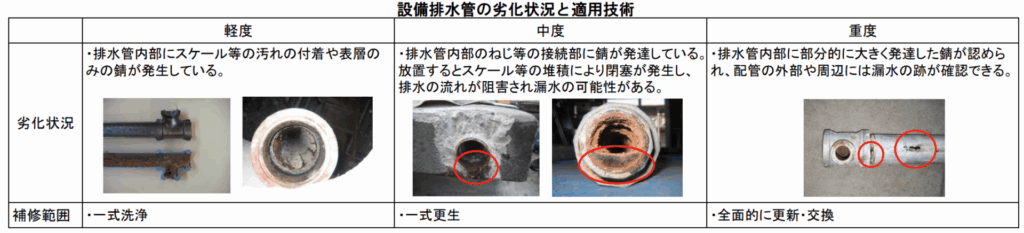
つまり大規模修繕工事は「建物の寿命を延ばす計画的な治療」とも言える重要なプロセスです。
正しい修繕の進め方を理解し、長期的な視点で建物の維持・向上を図ることが、居住者にとっても管理組合・オーナーにとっても大きなメリットとなります。
【株式会社マーク担当者のコメント】
最近は、単なる「建物の維持」ではなく、バリアフリー対応や省エネ改修を組み込む「価値向上型」の修繕計画も増えています。
▶ 大規模修繕工事の概要を詳しく知りたい方はこちらをチェック
▶ アパートの大規模修繕工事について知りたい方はこちらをチェック
国土交通省の「マンション大規模修繕ガイドライン」とは
これからアパートやマンションの大規模修繕工事を開始しようと考えている人がチェックしたいのが、国土交通省が公表している「マンション大規模修繕ガイドライン」です。
当ガイドラインには、計画的・透明性のある修繕工事を行うための「基本ルール」がまとめられており、修繕工事を進める際の手引きとして、多くの管理組合・オーナー・外部コンサルタントが参照しています。
参考として以下にガイドラインに掲載された主要ポイントをまとめました。
- 長期修繕計画の定期見直し(5年に1回推奨)
- 修繕委員会の設置と情報公開の徹底
- 工事発注方式は「設計監理方式(責任分離型)」を原則推奨
- プロポーザル方式や入札により業者選定の透明性を確保
- 工事後の検査・完了報告・次回計画の見直しも含めたPDCAサイクルの導入
上記からもわかるように、このガイドラインは、国が推奨する「失敗しない修繕工事の教科書」です。大規模修繕を実施する前にガイドラインをチェックしておけば、住民との合意形成や業者選定を、よりスムーズに進められます。
参照:国土交通省「長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改定)」
また以下より、ほかにもオーナー・管理組合がチェックしておきたい資料の概要を紹介します。
「大規模修繕工事の実態調査」の要点
アパートやマンションの大規模修繕では「修繕に関する情報不足」「意思決定の不透明さ」などで多くのトラブルが生まれています。そこで事前にチェックしたいのが「マンション大規模修繕工事に関する実態調査」です。
当調査は、実際に大規模修繕工事を行ったオーナーなどにヒアリングした情報がまとめられており、次の情報を数値としてチェックできます。
- 修繕頻度・回数
- 建物の規模感
- 工事費用
- 発注先の選定
全国平均の情報が掲載されていることから、今後の大規模修繕工事の目安となります。
なお、基本的にはマンションのみを対象とした調査であるため、アパートのオーナーは、金額や規模感を避け、頻度や回数などを参考すると良いでしょう。
参照:国土交通省「マンション大規模修繕工事に関する実態調査(令和3年度)」
「大規模修繕の手引き(ダイジェスト版)」の要点
大規模修繕工事の公的な情報は、国土交通省以外にも、住宅金融支援機構からも公表されています。そのなかでも、アパート・マンションのオーナーが参考にしやすいのが「大規模修繕の手引き(ダイジェスト版)」という資料です。
当資料は、本記事で紹介する工事の進め方や、動き方、注意点といったノウハウがまとめられています。参考として以下に、資料の要点を整理しました。
| フェーズ | 内容 | 主な作業 |
|---|---|---|
| 【1】企画・立案 | 工事の目的整理 | 修繕委員会設置・目的明確化 |
| 【2】計画・設計 | 設計内容の検討 | 設計事務所の選定・設計図作成 |
| 【3】発注・契約 | 業者選定 | 入札またはプロポーザル実施 |
| 【4】工事施工 | 工事監理 | 工事中の検査・進捗管理 |
| 【5】完了・報告 | 成果確認と報告 | 完了検査・住民報告・次回に向けた記録 |
オーナーおよび管理組合が「何をいつ判断するのか」を把握しやすい構成になっています。また「住民説明会のタイミング」や「情報公開の方法」についても具体的な記述があるため、大規模修繕工事のバイブルとしてPDFデータをダウンロードしておきましょう。
参照:住宅金融支援機構「大規模修繕の手引き(ダイジェスト版)」
大規模修繕工事の進め方【5ステップで解説】
大規模修繕工事は、正しい「進め方」を理解しておかないと、費用の増加や業者とのトラブル、住民との摩擦などにつながるリスクがあります。
そこで国土交通省や住宅金融支援機構の手引きをもとに、失敗を防ぐための大規模修繕工事の進行手順を5つのステップに分けてまとめました。
それぞれのステップでは「何をやるべきか」「どんな注意点があるか」を具体的に紹介します。
ステップ1|修繕委員会・協議会の設置
大規模修繕工事をスムーズに進めるためには、管理組合のなかに「修繕委員会」または「協議会」と呼ばれる実務担当チームを設置することが重要です。
大規模修繕は、専門性が深く、金額のことや住民対応について考えなければならず、管理組合(理事会)単独での運営には限界があります。そこで、住民有志や専門家も含めて設けられるのが「修繕委員会」や「協議会」です。
| 区分 | 主な構成メンバー | 役割 | 決定権 |
|---|---|---|---|
| 管理組合 (理事会) | 理事長・理事 | 法的な意思決定、予算承認、契約締結 | あり(最終決定) |
| 修繕委員会 | 理事 & 住民代表 | 修繕計画の検討、見積取得、情報整理 | なし(提案機関) |
| 協議会 (外部支援型) | オーナー・外部コンサルなど | 管理会社と連携した意見交換・調整 | なし(意見機関) |
なお、修繕委員会や協議会では、次のような具体業務を担います。
- 複数の設計事務所・業者の見積もりを比較
- 修繕の優先順位を検討(外壁・屋上・配管など)
- 住民アンケートの作成・回収
- 合意形成のための説明会の企画
- 理事会に提案資料を作成・報告
「委員会」は動く人たち、「管理組合」は決める人たち、というように役割分担を明確にすることで、住民や業者とのやり取りもスムーズになり、トラブルの未然防止につながります。
【株式会社マーク担当者のコメント】
修繕委員会は“地ならし役”、理事会は“承認機関”。この2つの役割を混同しないことで、工事も合意形成もぐっとラクになります。
▶ 大規模修繕協議会について詳しく知りたい方は、こちらもチェック
ステップ2|長期修繕計画の見直しと内容精査
大規模修繕を進めるうえで最初に見直すべきなのが「長期修繕計画」です。
アパートやマンションを建てた当初に作成した修繕計画が現状と合っていない場合、そのまま工事を進めると予算超過や不必要な工事項目が発生するおそれがあります。参考として以下に、見直しのポイントをまとめました。
| チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 修繕時期 | 前回の実施時期から年数が経過しているか? |
| 項目の優先度 | 本当に今やるべき工事か?(配管よりも外壁が優先かなど) |
| 費用見積もり | 最新の建築単価や人件費に基づいているか? |
| 施工履歴 | 過去の工事記録や保証期間は反映されているか? |
| 住民ニーズ | バリアフリー化やEV設備など新たな要望はあるか? |
国土交通省では「最低でも5~7年に1回は見直す」ことを推奨しており、実際の劣化状況や建材の寿命、物価変動を加味して調整する必要があります。
(参考:住宅金融支援機構「大規模修繕の手引き(ダイジェスト)」)
古い修繕計画をそのまま使うと、無駄な出費だけがかさみます。現在の建物の状態と、住民の将来ニーズを正しく把握したうえで、修繕内容を取捨選択することが、予算面でも住民満足度の面でも大きな差を生みます。
【株式会社マーク担当者のコメント】
特に注意すべきは「やらなくていい工事」を入れないことです。過剰な工事は住民の不満につながります。
ステップ3|コンサルタント・設計事務所の選定
大規模修繕工事は、誰に設計・工事監理を任せるかで大きく品質が変化します。そのため、第三者的な立場から技術的・契約的にサポートしてくれる建築士事務所や修繕コンサルタントの選定が重要です。
【コンサルタント・設計事務所の探し方】
・Web検索で特定の事務所を見つける
・提案書やヒアリングで評価して業者を選ぶ(プロポーザル方式)
・公募を出して価格競争をしてもらう(入札方式)
なお国土交通省のガイドラインでも、設計者(=コンサルタント)と施工業者の役割を分けることで、チェック機能を働かせて不正や施工ミスを防ぐために「設計監理方式(責任分離型)」の採用が推奨されています。
(参考:国土交通省「長期修繕計画作成ガイドライン」)
特に近年では、技術力だけでなく住民説明会での「伝える力」「柔軟性」も選定基準として重視されるようになっています。
施工業者を選ぶ前に、「誰に計画と監理を任せるのか」を決めることが重要ですので、「コンサルタント=施工の質と予算を守る盾」と考えて、信頼できるパートナーを選定しましょう。
ステップ4|施工業者選定と工事方式の決定
施工業者の選定は、大規模修繕工事の「品質」「費用」を左右する最大のポイントです。参考として以下に施工業者のチェックポイントをまとめました。
- 過去の施工実績(所有する物件エリアに強い実績など)
- 瑕疵保証やアフター対応の内容
- 見積書の内訳が明瞭か(人件費・材料費・共通仮設費など)
- 住民対応力(騒音対策・連絡体制・マナー)
なお施工業者は見積もりの価格だけではなく、実績や口コミ情報をチェックすることも重要です。複数業者に相見積もり(最低3社以上)を取り、同じ施工条件で比較をスタートしてみてください。
【株式会社マーク担当者のコメント】
“価格が安い=お得”ではありません。大切なのは「施工品質や実績」「説明の丁寧さ」ですので、そこを担保できる業者選定が成功の鍵です。
また株式会社マークでは神奈川県でアパートの大規模修繕工事を提供しています。同エリアで施工業者をお探しなら無料見積もりをご依頼ください。
▶ 株式会社マークに神奈川県のアパートの大規模修繕工事を無料相談する
▶ 詳しい施工事例をチェックしたい方はこちら
ステップ5|居住者説明・工事開始・完了報告
施工業者を見つけて工事をスタートしたら、居住者とのコミュニケーションに力を入れましょう。
着工前から完了報告までの情報共有が不十分だと、クレームや不満、トラブルの原因になります。問題を回避するためにも、次のような情報を共有しておきましょう。
| タイミング | 対応 |
|---|---|
| 工事前の情報提供 (着工前1〜2か月) | ・住民説明会 (2回以上推奨/休日・夜間開催など) ・工程表の配布 (週単位・日単位で予定を示す) ・ベランダや玄関使用不可日などの事前告知 ・騒音・臭気・粉塵のある作業日時の告知 ・問い合わせ窓口の設置と周知 (メール・掲示板) |
| 工事中のフォロー | ・エレベーター・共用通路などの制限告知 ・苦情対応の即時対応体制 ・週次・月次の「工事進捗のお知らせ」掲示 |
| 工事完了後の対応 | ・修繕完了報告書の配布 ・第三者(設計監理者)による完了検査結果の提示 ・今後の修繕予定や保証期間の共有 |
説明の回数が多すぎることを不満に思う人はいませんが、説明がなかったことに対する不満は根深く残ります。
トラブルが起きると工事の中止や延期などが起きるため、工事の品質と同じくらい、伝えることが重要だと覚えておきましょう。
【株式会社マーク担当者のコメント】
大規模修繕工事の手順が複雑で覚えきれないという方は、株式会社マークにご相談ください。手続きや大規模修繕の進行をサポートいたします。
▶ 株式会社マークに神奈川県のアパートの大規模修繕工事を無料相談する
大規模修繕工事を成功させるコツ
大規模修繕工事の失敗を回避したいなら「工事そのもの」だけでなく、準備・住民対応・専門家との連携といった「プロセス全体」に目を向けることが大切です。
参考として以下に、大規模修繕を成功させる5つのポイントをまとめました。
- 目的を明確にする(価値維持 or 向上型)
→ 長期視点でバリアフリー・省エネ改修も検討 - 信頼できる設計・施工業者と組む
→ 実績・説明力・アフター対応を比較して選定 - 住民との情報共有を徹底する
→ 工程表・説明会・掲示板・アンケートの活用 - 計画を柔軟に見直す姿勢を持つ
→ 経済状況や建物劣化に合わせて適宜調整 - 説明責任を忘れない(報告・記録)
→ 議事録・進捗レポート・写真記録で安心感を
修繕工事の「成功」とは、単に工事が終わることではなく、住民が納得し、将来のトラブルが減り、資産価値が維持・向上されることも含めなければなりません。技術力と同じくらい、進め方そのものが結果を左右するので、上記のポイントを押さえつつ動き始めてみてはいかがでしょうか。
【株式会社マーク担当者のコメント】
失敗の多くは「判断の早さ」よりも「準備の浅さ」が原因です。施工業者などから成功事例の情報を聞いたうえで、動いてみてください。
大規模修繕工事のスケジュール
大規模修繕工事のスケジュールは、一般的に1〜2年単位の長期工程となります。
「何から始めればいいか分からない」「準備にどのくらい時間がかかるのか不安」という方のために、管理組合やオーナーが把握しておきたい基本的な流れをまとめました。
| 時期(目安) | 主な作業 | 関連する主体 |
|---|---|---|
| 着工18か月前〜 | 修繕委員会の設置、長期修繕計画の見直し | 管理組合、委員会 |
| 着工15か月前〜 | 設計事務所・コンサルタントの選定 | 管理組合、外部専門家 |
| 着工12か月前〜 | 現地調査、改修範囲の確定、住民アンケート | 委員会、設計者 |
| 着工9か月前〜 | 工事費概算、施工業者の選定(プロポーザル等) | 管理組合、設計者 |
| 着工6か月前〜 | 住民説明会の実施、工程表の配布、仮設準備 | 委員会、業者 |
| 着工 | 実際の施工開始 | 施工会社、監理者 |
| 工事期間中(約3〜6か月) | 中間検査、進捗共有、騒音・使用制限対応 | 全関係者 |
| 工事完了後 | 完了検査・報告書提出・住民報告会 | 設計監理者、委員会 |
| 完了後1〜3か月 | アフター説明・保証内容通知・次回見直し計画 | 管理組合、施工業者 |
【株式会社マーク担当者のコメント】
スケジュールが1か月遅れると、費用が数百万円単位で増えることもあります。とにかく「着工の1年前」から逆算した準備が大切です。
大規模修繕でよくあるトラブルと回避策
大規模修繕工事では、工程や契約が適切でも、思わぬトラブルが発生することがあります。その多くは、「情報共有の不足」や「曖昧な業者選定」が原因です。
そこで以下より、よくある失敗例とその回避策を紹介します。
【トラブル1】管理組合との対立・情報共有不足
よくあるトラブル
・「知らないうちに修繕が決まっていた」
・「説明会がなかった」
・「必要な修繕とは思えない」
と反発される
回避策
・修繕委員会を設置する
・住民説明会を複数回実施する
・工程表・議事録・アンケートを配布・掲示する
・少数意見にも耳を傾ける「合意形成プロセス」を整える
【トラブル2】施工不良・手抜き工事の発覚
よくあるトラブル
・工事後すぐに漏水やタイル剥離が発生した
・完了後のチェックが甘く、瑕疵を見逃した
回避策
・設計監理方式の導入で「第三者」による品質監理を確保する
・工事中の中間検査・完了時の第三者チェックを徹底する
・瑕疵保証付きの契約内容とアフター対応を確認する
【トラブル3】追加費用の発生と契約トラブル
よくあるトラブル
・「追加工事が必要」と言われて予算を大幅オーバー
・見積に入っていない項目の請求が後から届く
回避策
・工事範囲・内容・条件を明文化した詳細な見積依頼
・見積書内訳の比較(人件費・共通仮設費など)
・追加工事には事前合意・議事録残し・再見積もりが鉄則
▶ 大規模修繕工事でよくあるトラブルをより詳しく知りたい方はこちら
よくある質問(FAQ)|アパート・マンションの補助金活用で失敗しないために
大規模修繕工事は、まず何から始めればいいですか?
まずは現状の「長期修繕計画」が今の建物状態に合っているかを確認し、修繕委員会の設置から始めるのがおすすめです。そこから予算の見直し、専門家の選定、住民との合意形成と段階的に進めていきましょう。
国土交通省のガイドラインに沿った進め方とは?
国交省のガイドラインでは、長期修繕計画の定期見直し・設計と施工の分離・情報公開の徹底などが推奨されています。特に設計・施工を別の会社が担当する「設計監理方式」の採用が推奨されており、トラブル防止や品質確保につながります。
大規模修繕工事の業者はいつ、どのように選べばいいですか?
設計事務所やコンサルタントを選んだ後に、施工業者の選定を行うのが基本です。業者は相見積もりを取り、過去実績・瑕疵保証・住民対応力を比較して決めましょう。着工の1年前から準備するのが理想です。
大規模修繕中、住民はどのように過ごせばいい?
騒音やベランダの使用制限など一定のストレスは避けられませんが、事前に説明会や工程表で情報共有がされていれば、安心して生活できます。管理組合はこまめな掲示・相談窓口設置などの対応を徹底しましょう。
大規模修繕工事を管理会社にすべて任せるのはNG?
管理会社に任せきりにすると、価格比較や第三者監理が不十分になるリスクがあります。専門家の意見を取り入れ、管理組合としても判断・確認を行うことで、コストと品質の両立がしやすくなります。
大規模修繕工事は正しい進め方を把握してからスタートしよう
大規模修繕工事は、建物の寿命を延ばし、資産価値を守るための重要なプロジェクトですが、進め方を間違えると、費用の増加や住民トラブルなど思わぬ問題に発展する可能性もあります。
だからこそ、国土交通省のガイドラインや各種手引きをもとに、正しい手順と体制づくりを整えてからスタートすることが大切です。
株式会社マークでは、アパートやマンションの大規模修繕をサポートしていますので、進め方に不安がある方はお気軽にご相談ください。
【株式会社マークからのご案内】
株式会社マークでは、神奈川県内のアパートを対象に、大規模修繕工事を見据えた建物の「無料点検」「補修相談」を承っております。「まだ直さなくても大丈夫?」という軽微な状態でも、お気軽にご相談ください。
監修・執筆|この記事は株式会社マークの編集チームにて作成しております。なお掲載している国・住宅金融支援機構等の情報は最新情報にもとづき適切に編集を実施しています。
