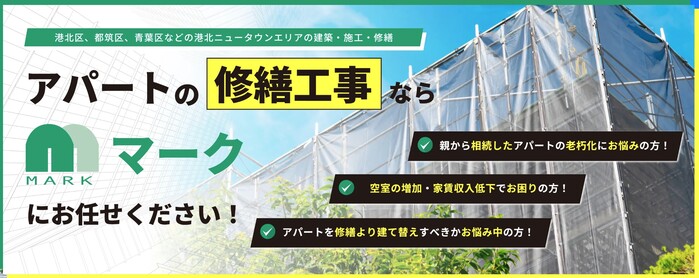コラム
【オーナー必見】アパート外壁の剥がれは放置NG!原因・費用・保険対応まで徹底解説|2025年最新版

アパートやマンションの外壁が剥がれているのを見かけたことはありませんか?
「見た目が悪いだけだから急がなくてもいい」と考えていると、それが雨漏り・空室率の悪化・損害賠償トラブルにまで発展する可能性があります。
そしてこの記事では、外壁剥がれの主な原因と放置によるリスク、補修方法や費用相場、火災保険の適用範囲まで、2025年現在の最新事情に基づいてわかりやすく解説します。
アパートやマンションを複数戸を所有するオーナーは、資産価値の維持や入居者満足度の確保に直結する重要テーマですので、今すぐチェックしてみてください。
なぜ外壁が剥がれるのか?オーナーが知っておくべき主な原因
アパートやマンションの外壁が剥がれる原因は、自然劣化だけでなく施工時の不備や建物の立地環境など、複数の要素が絡み合って起こるものです。
ここでは、特に多い3つの原因について具体的に解説します。
【原因1】経年劣化と紫外線・雨風による塗膜の劣化
外壁塗装の寿命が切れると、塗膜が浮き・ひび割れ・剥離を起こす原因になります。
外壁塗装やタイルの耐用年数は一般的に8〜15年程度とされており、それを超えると塗膜の劣化が顕著になります。
(参考:株式会社佐藤公式サイト、株式会社リームー公式サイトなど)
特に、南向きの外壁は紫外線の影響を強く受けやすく、チョーキング現象(粉吹き)→ヒビ→剥がれという劣化の流れが起こりやすい傾向があります。アパート・マンションが築5年以上を経過している場合には、一度建物診断を受けておくのがおすすめです。
【原因2】モルタルやサイディング材の施工不良
新築から数年で剥がれが発生した場合、「施工ミス」が原因の可能性もあります。
特にモルタル壁の場合には、下地処理の不十分さや養生不足が原因で、塗膜がしっかり密着せず、早期に浮き・剥がれが起きることがあります。また、サイディングボードの継ぎ目のシーリング不良も、雨水が浸入する原因になるので注意が必要です。
築浅で剥がれが発生した場合は、施工不良を疑い、保証書の確認や業者との交渉をスタートしましょう。
【株式会社マーク担当者のコメント】
場合によっては、保証期間を過ぎて対応してもらえないケースもあります。その際には、新しく施工業者を探さなければなりません。
【原因3】換気不良・湿気・立地特性による局所的なダメージ
見えにくい場所の外壁剥がれは、湿気の滞留や環境要因によるケースが多いです。
北側や日陰になりやすい面では、結露やカビの発生、湿気のこもりによって塗膜の内部劣化が進行します。また、沿岸部では塩害、山間部では風雨の吹き上げなど、立地による特有のダメージも見落とせません。
表面には現れにくい劣化要因ですので、定期的に建物診断を受けることが重要です。
【株式会社マーク担当者のコメント】
マークが対応している神奈川エリアは、海沿い・山沿いに面している地区が多いため、特にこの劣化要因が多いです。
「これって剥がれの初期症状?」
と不安な方は、無料の修繕診断をご利用ください。
神奈川エリアのアパートをサポート
※「記事を見た」と伝えていただくとスムーズに対応可能です
【TEL:045-948-6525】
ほかにどんなトラブルが起きるか気になっている方は、以下の記事もチェックしてみてください。
外壁剥がれを放置したらどうなる?オーナーが負うリスクとは【事例あり】
外壁の剥がれを「見た目だけの問題」と軽視してしまうと、思わぬ損失やクレームを引き起こしかねません。放置すればするほど建物の劣化は進行し、結果的に修繕費用やリスクが大きく跳ね上がってしまう可能性があります。
ここでは、実際のトラブル事例を交えながら、外壁剥がれを放置したことで起こる3つのリスクを解説します。
【リスク1】入居者からのクレーム・資産価値の低下
外壁の剥がれが目立つと、見た目の印象が悪くなり、次の低下に直結します。
- 入居者の満足度(定着率)
- 新規の成約率
剥がれた外壁は、入居希望者から「管理が行き届いていない物件」と見なされやすく、空室率の上昇や賃料の値下げ圧力を招くことも少なくありません。また、不動産業者によっては、内見時点で「外壁の劣化があるので交渉対象」として扱われるケースもあります。
空室・賃料・資産価値すべてに波及する経営リスクですので、アパート・マンションの早めの修繕が必要です。
事例|放置したせいで空室率が上昇
あるオーナーの事例では、内見時に入居希望者から「ここ大丈夫ですか?」と聞かれたことが増えたといいます。外壁の一部に剥離が見られただけでも、「この物件、雨漏りとかないですよね?」と入居前から不安を抱かせる要因になっていたのです。
その結果、半年間で3戸が空室に。修繕後は「見た目もきれいで安心」との声が入り、1か月以内に全戸成約に至りました。
【リスク2】外壁材の落下事故 → 損害賠償リスクも
剥がれた外壁が落下すると、通行人や入居者への人的被害につながる可能性があります。
外壁材(モルタル・サイディング・タイルなど)の浮きや剥がれが進行すると、風や振動で自然落下する危険性がある点に注意が必要です。実際に、国土交通省でも、タイル等の落下死亡事故について言及されています。
(参考:国土交通省「外壁タイル等落下物対策の推進について」)
また、ケガや死亡事故につながった場合には、高額な損害賠償リスクも発生します。
YouTubeなどでも、事故情報が複数アップされているので、一度確認をしたうえで早めの外壁修繕をスタートしましょう。
事例|住民や通行人にけがをさせた
国土技術政策総合研究所が公開している「建物事故予防ナレッジベース」によると、これまでに219件もの外壁等の落下事故が起きています。つまり、「いつか誰かがケガをするかもしれない」は、もはや他人事ではありません。
【事故概要1】
アパートの階段の壁が崩れ、ボロボロ崩落してきた。しばらくして補修工事の足場が組まれたが、1ヶ月近く足場だけで作業が始まらず放置…
【事故概要2】
築8年の木造3階建てアパートの外階段の一部が崩れ、1階から2階に上っていた女性が地面に落ち、外因性脳挫傷により5日後に死亡した。…
「事故が起こる前に対策したい!」
それなら、マークの無料の修繕診断をご利用ください。
神奈川エリアのアパートをサポート
※「記事を見た」と伝えていただくとスムーズに対応可能です
【TEL:045-948-6525】
【リスク3】剥がれが雨漏り・内部腐食へ発展するケース
外壁の剥がれは、雨水の侵入口になり、内部構造の腐食やカビを引き起こす原因になります。
特にモルタル外壁では、ひび割れや剥離部分から雨水が浸透しやすく、壁内部にシミや黒カビが広がったという事例が多数あります。目に見える剥がれを放置すると、目に見えない重大な損傷が広がるリスクがあるので注意しなければなりません。
事例|アパート・マンション全体の劣化が早まった
関東エリアに築25年のアパートを所有するオーナー様は、1階部分の塗膜剥がれをその状態のまま2年放置されていました。その後、特に事故などは起きなかったものの、壁内結露と構造材の腐食が発覚。1棟全体で250万円の修繕が必要になりました。「もっと早く手を打っていれば、5分の1で済んだ」と公開されていました。
また、実際に雨漏りも発生している方は、以下の記事がおすすめです。
外壁剥がれの補修方法と費用相場
外壁の剥がれが発生した場合、「どこまで直すべきか」「費用はどれくらいかかるのか」と悩む方は多いでしょう。
実際の補修方法は、使用されている外壁材の種類(モルタル・サイディング・ALCなど)や劣化の程度によって変わります。
ここでは、代表的な外壁材ごとの補修方法と費用目安を解説します。オーナーとして無駄な支出を避けるためにも、素材別の違いと費用感を把握しておくことが重要です。
モルタル外壁の補修方法と材料費・工賃目安
モルタル外壁は、ひび割れや塗膜の剥がれが進行しやすいため、状況に応じた部分補修が基本です。
特に、表面の塗膜が浮いて剥がれたり、下地にクラック(ひび割れ)が生じていることが多いため、まずは浮いた部分の撤去→下地調整→再塗装の工程が必要になります。
費用目安(モルタル補修)
| 項目 | 費用相場(目安) |
|---|---|
| 小規模補修 (1〜3㎡程度) | 2万〜5万円 |
| 中規模補修 (3〜10㎡程度) | 5万〜15万円 |
| 広範囲 (外壁面全体塗装) | 70万〜120万円(30坪) |
主な補修手順
- 剥がれ部分を削って撤去
- 下地にカチオン系モルタルやシーラーを施工
- パテ処理または補修材で埋め戻し
- 下塗り・中塗り・上塗りの3工程塗装
モルタルは柔軟性に乏しいため、一度の補修で終わらず数年後に再補修が必要になるケースも多くあります。長期視点で費用を考えることが大切です。
サイディング・ALCの補修方法と材料費・工賃目安
サイディングやALCパネルの外壁は、表面だけでなくつなぎ目のコーキング(シーリング)の状態も補修の鍵になります。
これらの外壁はパネル状の素材を張り合わせて構成されているため、シーリング材が劣化して雨水が侵入→接着不良や反り→塗膜剥がれ・素材の膨れが発生することがあります。
費用目安(塗装・打ち換えなど)
| 補修内容 | 費用相場(目安) |
|---|---|
| 塗装補修 (10㎡前後) | 5万〜12万円 |
| コーキング打ち替え (30坪) | 10万〜25万円 |
| 部分張替え (1枚) | 2万〜6万円/枚 |
| 全面張替え・カバー工法 | 150万〜300万円(30坪) |
主な補修手順
- 軽度の剥がれ:塗膜の再塗装(高圧洗浄→3回塗り)
- 中程度の損傷:一部張替え+再塗装
- 重度劣化:全面張替えまたは外壁カバー工法を検討
サイディングの剥がれは、「表面の問題だけに見えて実は下地の腐食が進行していた」というケースが多いため、プロによる調査と正確な劣化診断が欠かせません。
どこまで補修すべきか迷っている方へ
まずは、マークの無料見積もりをご利用ください
※見積もりだけでもOK
神奈川エリアのアパートをサポート
※「記事を見た」と伝えていただくとスムーズに対応可能です
【TEL:045-948-6525】
また補修のお金がないという方は、以下の記事もチェックしてみてください。
アパート・マンションオーナーがとるべき外壁メンテナンス戦略
外壁の剥がれは、発見後に修繕する“後追い対応”では費用が膨らみがちです。
そのため、賃貸物件を管理・所有するオーナーにとっては、築年数・劣化状況に応じた「計画的な外壁メンテナンス戦略」が、建物の資産価値を保つうえで非常に重要となります。
なぜ戦略的なメンテナンスが必要なのか?
外壁は常に紫外線・雨風・排気ガス・気温差などのダメージを受け続けており、塗膜や外壁材の劣化は避けられない現象です。
国土交通省が公表している「長寿命化修繕計画ガイドライン」においても、外壁の点検・再塗装は12〜15年ごとの定期実施が推奨されています。
(参考:国土交通省「長期修繕計画作成ガイドライン」p.80)
築年数に応じた補修・点検のタイミング
| 築年数 | 外壁の劣化傾向 | 推奨メンテナンス |
|---|---|---|
| 5〜10年目 | チョーキング・色あせ | 点検+再塗装検討 |
| 10〜15年目 | クラック・塗膜浮き | 再塗装+部分補修 |
| 15〜20年目以降 | 剥がれ・コーキング割れ・漏水 | 塗装全面+張替え・再シーリング |
外壁メンテナンスを怠ると、資産価値の低下・空室率の上昇・剥離事故による賠償責任など、建物経営に直結するリスクを抱えることになります。
また、外壁塗装などの修繕をするタイミングを詳しく知りたい方は、以下の記事がおすすめです。
修繕計画に外壁を組み込むメリット
外壁剥がれが起こるたびに対応していると、突発的な高額修繕が発生しやすくなります。
一方で、長期修繕計画の中に「外壁塗装・補修の時期と予算」を組み込んでおけば、予防的な補修で結果的にコストを抑えることが可能です。
【株式会社マーク担当者のコメント】
実際に管理会社や大規模修繕コンサル、施工会社の多くが、築10年目と15〜20年目に大規模外壁対策を実施すべきと提案しています。神奈川県版ですが、詳しいタイミングは以下の記事をチェックしてみてください。
外壁剥がれに関するよくある質問【FAQ】
火災保険が適用される剥がれとされない剥がれとは?
「台風による飛来物で外壁が割れた」「強風・突風で外壁が一部剥がれた」「大雪の重みでサイディングが落下した」といった外部の影響による外壁の葉枯れは保険で補償されるケースが多いです。一方で、「経年劣化で塗膜が浮いた・剥がれた」「築20年以上経過した建物の自然劣化」「施工不良が原因と見なされた」といった場合には保証されないケースもあります。
外壁が剥がれてもすぐ直さなくてもいい?
早めの対応が推奨されます。外壁の剥がれを放置すると、そこから雨水が侵入し、建物内部の腐食やカビの原因になります。また、劣化が進行すると補修範囲が広がり、結果的に修繕費用が増加することも。小さな剥がれでも放置せず、まずは専門業者に点検を依頼するのが安心です。
DIYで直しても火災保険は使えますか?
原則として自己修繕では保険対象外になります。火災保険での修繕費補償には、専門業者による「被害報告書」や「見積書」の提出が求められます。DIYでの補修では被害の客観性が担保できず、保険会社の判断で申請が通らないケースがほとんどです。保険活用を考えているなら、専門業者に相談しましょう。
外壁剥がれの修繕で費用対効果がいいのは?
劣化が軽度なうちに部分補修するのがコスパが良いです。外壁全体の塗り直しや張替えは高額になりますが、小規模な剥がれであればパテ処理や部分再塗装で5万〜15万円ほどに抑えられます。劣化の初期段階で対応すれば、建物全体の寿命延長にもつながり、トータルで見ても費用対効果は高くなります。
まとめ|外壁の剥がれは「早期対応」が資産価値を守る
外壁の剥がれは、見た目だけでなく建物全体の耐久性や空室リスクにも影響する重要なサインです。
経年劣化や施工不良、気候によるダメージなど原因はさまざまですが、放置すると修繕費は倍以上に膨れ上がることもあります。
だからこそ、軽度のうちに発見し、プロに診断してもらうことが最大の節約策です。費用対効果を高め、資産価値を守るためにも、まずは一度、専門家の目で現在の状態をチェックしてもらいましょう。
監修・執筆|この記事は株式会社マークの編集チームにて作成しております。なお掲載している国・自治体の情報は最新情報にもとづき適切に編集を実施しています。